|
|
 |
放射線安全に係る妄信を排そう
加藤和明
2015年03月30日 |
福島原発事故から4年過ぎたというのに「安全神話」の放逐も「危険神話」の放逐も未だ不十分であり、復興への困難は今も続いている。 困難の最大の要因は、“放射線との付き合い方”についての“万人が納得できる考え”を、未だ国が示すことができずに居るからである。
世の中にはいろいろの専門家(自称、他称、偽称、詐称、等々)が居り、この 4年間、これら専門家たちは“百家争鳴”を続け、一般人にとっては(禁止用語が加わるが)“群盲象を撫でる”の状態であった。
これまでも筆者が度々強調してきたことであるが、(「~は~である」といった)記述命題の正誤や判断・行為の当否は、前提に依存して決まることである。
ある視点に立ったときや対象をある領域に限定したときには、“正確に”もしくは“概ね”正しいと思われる言説であっても、適応を欠いている事例が、こと放射線安全確保に係る方策に関しては、多すぎるように思われてならない。
表題に掲げた妄信や妄想、迷信、適用領域についての誤った思い込み、などを排することに、関係者はもっと意を尽くすべきである。
以下に筆者が考える代表例を示し、参考に供したい。 何回かに分けることになろうかと思うが、一応、順不同としておく。 筆者自身に“妄信”や“誤った思い込み”がないとは断言する勇気はないので、ご意見・ご異見がお在りのときは、お聞かせくださるよう予めお願いするものである。
<1> 放射線の被曝量は線源からの距離の 2乗に反比例して少なくなる
被曝対象の物体と放射線源が共に“点状”とみなされる場合にのみ成り立つ話です。 物体と線源が真空の自由空間にあるときには、線源が無限長の“線状”であるときには“距離の
1乗に反比例”となるし、無限平面状であったら“距離の 0乗に反比例”すなわち距離に関係しなくなります。 「距離・時間・遮蔽」を放射線防護の“黄金律”として受け止め、“カタチ”だけ使うと、例えば指先に放射性物質がほんの少量付いたときでも線量率が無限大になると思って必要以上に怯えてしまうことになります。
<2> 放射能には“半減期”というものがあるので、幾ら時間が経っても放射能というのは永遠に消えることがない
放射能というのは未来に係る可能性の期待値であり、その値は非負の有理数となるので、幾らでも小さな値を持たせることができる。 一方、放射能というのは放射性核種の属性である。放射性核種の実体は“安定性を欠く原子核”であり、それは非負の整数で表されるものである。
時間の経過と共に→ 3→ 2→ 1と数は減少して行き、最後は 0(ゼロ)である。 数がゼロということは放射性核種が消滅したことを意味し、属性であるに過ぎない放射能もこのとき消滅するのである。
<3> 放射線の(被曝管理のために国が定めた)管理基準は、放射線の種類や被曝の様態の如何を問わず、適用されるべきものである
今日、この国において国民が受ける放射線被曝は、①.医療放射線被曝:疾病の診断・治療を目的に医療行為を受けることに付随してうける放射線被曝、②.環境放射線被曝:出自の如何を問わず環境に存在する浮遊放射線への被曝、③.職業被曝:国が使用等に対して許認可を与えた“特定の放射線源”に起因する放射線への職業的被曝の3種類に分類できる。
放射線防護に係る国の制度設計では、③の国が使用等に対して許認可を与えた“特定の放射線源”に起因する放射線への被曝のみが対象とされていて、職業的被曝は“職業人”が(放射線)管理区域内で作業することにより受ける被曝は、(国の指定する方法で行われる)個人線量の測定・評価によって管理し、“職業人”に指定されない者に対する被曝は、環境放射線量への寄与を一定の限度内に抑制することと、管理区域内への入域を条件付で制限することが、基本的方策とされて居る。東日本大震災によって東電福島原発が過酷事故を起こした後、「事故起因放射性物質」が上記“特定放射線源”に追加され、それによる環境汚染の除去等に“職業的”に関わる者の安全確保策として、従来から存在する「電離放射線防護規則(略称“電離則”)」に並べて「除染“電離則”」がつくられている。
<4> 線量と(いうもの)は“放射線が(人体など)物体や物質に及ぼす影響”を科学の対象として扱うために導入されたものであり、放射線防護の目的に使われている実効線量は、放射線が人体に及ぼす影響の表現体と見做してよい
現在、放射線防護の現場において実際上防護の目標に据えられているのは、ICRP(「国際放射線防護委員会」と訳されているが、正確には「Ionizing
RadiationのRadiological Protectionを目的として医学界が設立した国際Commission」である)が Stochastic
Effect(確率的と訳されているが、確率論的と訳すほうが適切と思われる)と呼ぶ“障害”の“発症リスクの上昇”を一定限度内に抑制することである。
実効線量は、出来栄えの良否は別として、このリスクの“表現体”と見做すべきものであって、影響そのものの表現体ではないのである。
一般に線量の測定・評価に関しては、望む限り任意の品質で測定評価ができるものでなければ、計器や評価法の示す結果の品質が判定できないものであり、その意味で、絶対測定(定義に忠実な測定)が適わぬ量は“測定不能の量”となる。
実効線量は、この“測定不能量”であり、ICRPは曲がりなりにも測定・評価が可能な“代替品”として、放射線防護の実務において必要となる 2つの主要な使用目的に合わせて、「周辺線量当量」と「個人線量当量」という
2種類の“実用線量”を導入した。 これら実用線量は ICRUの導入した人体模型の定点における等価線量として定義され、空間線量の評価には放射線場の様態依存を排することと、個人線量の評価には“実際上人体正面からの入射が多い”ことが考慮されている。
然しながら、わが国においては、両者を統一的に扱って、実効線量に対する実用線量としては「1cm線量当量」 1種類のみを導入している。 その定義や測定・評価についての詳細な規定は法令に盛り込まれず、(放射線障害防止法)施行規則の別表に、代表的な透過性放射線である光子と中性子を取り上げ、一定のエネルギー領域から代表的なエネルギー値を取り出し、前者については「“(自由空気中)空気カーマ”の単位量あたりの“1cm線量当量”値」、後者については「粒子フルエンスの単位量あたりの“1cm線量当量”値」が、換算係数として使用するように定められている。
“(自由空気中)空気カーマ”というのは、戦前から使われ、放射線計量の国家標準とされてきた、Exposure(わが国では照射線量と訳される、電気量で定義された線量のこと。
単位には roentgen,R,が使われていた)を“エネルギー量”を使って書き直したものである。
周辺線量当量も実際上“実測不能量”であるので、法令取り入れに際して見送ったのは結果として望ましいことであったかもしれないが、“1cm線量当量”を“(自由空気中)空気カーマ”の関数と見做して使わせるとなると、光子場については“(自由空気中)空気カーマ”のエネルギースペクトルを知らなければ正確な評価はできないことになる。
両量の比がエネルギーに依らず一定とはならないからである。
今日、この国の制度設計が採っている“1cm線量当量”測定器等の較正法は、線量計の表面側に標準線源等から発せられる標準放射線を平行平面状に照射し、同じ場所に置かれた“(自由空間における)空気カーマ”測定用の標準計器の指示値との対比により行うというものである。
換算には、上記告示別表から、用いた放射線に相当する換算値を取り出して行うことになる。 一方、この国には、法令に順ずるものとして扱われる JIS規格(日本工業規格)というものがあり、そこでは「空間線量」の測定には“(自由空気中)空気カーマ”を使い、「個人線量」の測定には、30cm×30cm×15cmの形状で
ICRU組織等価物質(実際には水 and/or プラスチックが使われる)よりなる平板ファントムの表面における“空気カーマ”を用いることとしていて、JIS-Z4511(2005)では「実用空気カーマ」と呼んでいる(同書:3-a-1)。
“3.11”の後、“特定放射線源”に指定された“福島原発事故起因放射性物質”により汚染された環境での“環境放射線”の“追加線量”に寄与する放射線は、線量計の較正に際して使われたであろう照射の様態とは大きく異なるものであり、空中に浮遊するガンマ線はエネルギーについても角度についても、そのスペクトルは大きく異なっている筈である。
空間線量の測定・評価を目的に使われる測定器や測定装置の“応答”には、(許容度を越す)角度依存性があってはならないが、実測されたデータや品質保証に係る情報を提示している例を殆ど見ない。
測定・評価の対象に実際上「照射線量」である“(自由空気中)空気カーマ”を使うとしている現行の“国策”も例外ではない。 仮に、Cs-137放出γ線が較正に使われたとして、入射放射線がそのγ線と同じと仮定し(品質管理上問題とされるべきケースは少なくない)“告示別表”にある
660keV相当の換算係数を使って、法令の求める測定・評価の対象量である“1cm線量当量”としているとしても、応答に角度依存性があってはならないのである。
放射線防護のための制御量の定量とそれを基に行う“状態”の判定について、国は品質の要求基準を示すべきと考えるが、その重要性がより高まっている今日においても、それが国民の目に見える形で示されていないことは、重大であると考える。
職業被曝の管理が、いわゆる“追加線量”でなされるのに対し、公衆の被曝管理は環境保全を手段として行ってきた。その際、環境放射線の線量率が“追加線量”込みで行われるのが通例であることも世の混乱に輪を掛けている。
関係者に問題を把握する能力が欠落しているか、問題は把握されているのに適切な処置がとられないまま時間が経過しているものと思われるが、その責任がどこにあるのかも不明確になっている。
“職業被曝”や“環境放射線被曝”の測定・評価には、高度に専門的な知識や技能が求められる。 (放射線防護に係る)国の制度設計において重要な位置を占めているこれらの仕事が、国家資格も必要とせず、国などの許認可も必要とされないというのは、いろいろの規制でがんじがらめとなっている感のあるこの国では、そもそも極めて稀有なことであるといってよい。
<5> 線量の評価値が同じであるならば、外部被曝であろうと内部被曝であろうと、受けるリスクに違いはない
線量という言葉が同じように使われるが、その中身(実体・定義)は別物である。内部被曝の場合は、放射性物質摂取の時点から将来にわたって(通常は期間として
50年とか 70年がとられる)受けるであろう(体内からの)被曝線量の時間積分を意味する(“預託線量”と呼ぶ)。放射線管理業務の軽減化を目的に、ある年の職業被曝線量の評価には、その年に受けた預託線量も加算して行うことが許されているが、リスクの表現体として眺めるとき外部被曝による実効線量と内部被曝による実効線量は等しくならない。
加えて、実際のリスク要因(外部被曝の場合は“放射線の量”であり、内部被曝の場合は“放射性物質の量”)から実効線量の値を算出は、モデルを設定してのシミュレーション計算によって行っているが、内部被爆の場合には計算のステップが、いってみれば一つ多く、使われるパラメータの数も多くなって居るので、安全係数が“より大きく”採られているといってよいのである。
リスクは、未来に係る可能性の測度であり、それは時間の経過と共に(数学的に言えば単調に)減少して行くものであるが、その様相も、外部被曝と内部被曝では異なっているのである。
したがって、被曝の時期が同じで線量の評価値が同じであったとしても、実際のリスクは内部被曝の方が小さいのである。 両者同じとする解説が少なくないが、それは「放射線管理の世界ではそのように割り切って考えている」ということに過ぎない。
なお、ICRPでは、体内に取り込まれても沈着することなく一過性で排出される気体状の放射性物質をも内部被曝の範疇に取り入れ、身体が半無限状の一定濃度気体にあるとしたときの“外部被曝線量率”から濃度に係る限度を定めて使用を勧告しているが、これは方法論として根本的に誤っているものである(外部と内部の重複規制)。
<6> わが国の(放射線防護に係る)制度設計は、ICRPの勧告に準拠してつくられているので、勧告が改定されたときには、関係法令への取り込みが未了であっても、(制度の運用に当たっては)そちらの規定に従うのが望ましい
わが国は“法治国家”を標榜し、仮に“出来の悪い法”や“悪法”であっても、これを守ることが国民に義務付けられている。 福島の原発が過酷事故を起こしたとき、わが国の制度設計では“想定外”とされていた事態が、放射線防護の世界でも出現したが、(当時の)制度設計で、適用してはよくない部分についての“効力停止”や、早急に対策を講じるべき“事項”への対応策を講じる必要が認められたが、そのために必要な“非常事態宣言”が発せられることもなく、“その場しのぎ”の施策が多くなり、結果として災害の規模と復興の経費を大きくしてしまったと言える。
一方で、ICRPの基本勧告改定の度にそれを全て忠実に法令に取り込んできたかといえば、そんなこともないのである。 潜在被曝への対応や航空機乗務員等に対する対応、緊急時の被曝管理基準値の設定など、がその例に入る。
ICRPの最新の基本勧告は 2007年勧告と呼ばれるものであるが、法令への取り込みは未だなされていない。 であるにも拘らず、これを手がかりに意見を表明する“(自称)専門家”が多数出現したことにも注意を呼びかけたい。
<7> 放射線への被曝による発癌リスクの上昇は、実効線量で表される被曝線量に正比例する
「単位量の実効線量が齎す“発癌リスクの上昇”は(線量の値に拘わらず)一定である」というのが、いわゆる LNTモデルと呼ばれるものの内容である。
我が国が放射線防護に係る現行の制度設計を行った当時(1950年代後期)には、吸収線量、すなわち電離の生成と言う形態による物質系へのエネルギー付与の密度、に比例して
DNAに傷ができ(A)、その量に比例して染色体異常が生じ(B)、さらにはそれに比例して突然変異が起こる(C)、と見做されていた。
しかし、その後得られた放射線生物学的知見により、今日では上記 ABCの比例関係のうち、Aは兎も角として、BとCの存在はともに否定されることが知られている(渡邊正巳・京都大学名誉教授が長崎大学在職中に茨城県立医療大学で拝聴した講演、などによる)。
人体には、様々なレベルで、生命維持に不都合な“キズ”を修復する機能を備えていることが分かったのである。
ICRPが創り上げた放射線防護のシステムは、年線量を制御の基本に据えている。このような長いタイム・スパンで被曝量の制御を行うとなると、線量の測定・評価に必要となるのは、通常それより短い時間について測定が行われることの多い線量という量に“加算性”を持たせることである。これが、ICRPが
LNTモデルから簡単に脱却できない原因の一つとなって居るようにも思われる。
年あたりの線量というのも“線量率”の表現法の一つであるが、いわゆる線量率効果を取り扱うには不適切に長いものである。 “分”線量で線量率を取り上げると、ICRPのいう確率論的影響の発症の可能性への線量率効果が顕著となり、現行の方策は“合理的とは言えない程、あまりにも安全側”につくられているという指摘もある(例えば、当フォーラムの顧問をお願いしている田ノ岡宏・元放射線影響学会会長)。
年線量限度をベースとした現行の方策を維持するにしても、例えば、“時間”線量を測定・評価の基準量とし、ある限度を超えたもののみを集計して“年線量”とし、“年限度”との比較は、これをもって行うという“制度上の変更”がなされてもいいのではなかろうか。
なお、岩波の月刊誌「科学」の 2014年5月号の 0491頁に、1F原発の国会事故調委員を務められた崎山比早子氏が「全固形がんに対する線量あたりの過剰相対リスク」というタイトルの図を載せており、横軸に対数で目盛った線量(Gy)、縦軸に“単位線量Gy”あたりの過剰相対リスク(ERR)をリニアメモリで示し、1Gy=1Svとした上で、100mSv以下の線量域でERRが大きく上昇すると訴えているが、この作図には数学的処理の観点から問題があると考える。
数式にする便宜上、ERRなる量を y、線量を xであらわすことにすると、横軸の変数に x’=log(x/x0),を使うなら、縦軸には、y(x)=dy/dx(x)ではなく、y’(x’)=dy/dx’=x(x’)・dy/dx(x’)を採用すべきである。そうでないとxが小さくなるにつれ
yが大きく表示されてしまうからである。 ここで、x0は変数 xを変数 x’に変える際に用いる基準線量値である。 LNTモデルでは勿論 yは xの関数とならず一定値となる。崎山氏は、y/xが一定とならず、xの値に依存することを示すことにより、ICRPが採用している
LNTモデルの不適切さを示したかったものと思われるが、この図は、多くの読者に誤った情報を伝えることになると考える。
<8> 放射線への被曝量(線量)は少なければ少ないほど良い
旧労働省がつくった「電離放射線障害防止規則」(通称“電離則”)が、第1条の基本原則に、そのようなことを書いていることもあり、そう思い込んでいる人が実に多い。
しかし、これは、国が使用等を規制している“特定の放射線源”のよる“職業被曝”を対象にしたものであると理解すべきものである。
“少なければ少ないほど良い”という哲学が示す最終の“理想”は被曝 free、すなわち被曝線量ゼロである。 これは、安全学の視点から言うと、実際上意味を持たない、安全論では、絶対的安全は追及しない。
例えば、自動車や飛行機の事故を皆無にするため、使用を止めるようなことはしないのである。
加えて、我々は、様々の起因放射線からなる環境放射線や医療施設で受ける放射線の被曝から逃れることはでいないことにも留意すべきである。
<9> 医師や看護師やその他のパラメディカルの人達を含め、医療界で働く人の受ける放射線被曝を「医療被曝」という
ICRPがつくった Medical Exposure(という言葉)を呼んだものを、わが国では「医療被曝」と訳し使っている。 しかし、ICRPがこの言葉に込めた“概念規定”は、患者が診断とか治療といった医療行為を受けるに際して受ける放射線被曝のことであった。
ICRPは、数回前の基本勧告改定で、学術の進歩のために行われる“志望者の放射線被曝”や医療現場での“介護者”が受ける被曝に対しても考慮すべしと勧告したのに対し、日本では放射線審議会が、この両者を“医療被曝”に含めることを決した。
それに驚いたかのように、ICRPでは最近「Patient Exposure(患者被曝)」と表現を改めたようである。
今現在もそんなに変わって居ないと思われるが、CTが世の中に出て以来、日本はその保有数において常に世界一であり続けた。 それに対するやっかみかと思うくらい、海外の医学界では、日本が健診に
CTを使って国民線量を高めて居ることに批判的な意見をいう人が多い。
何れにしても、“医療被曝”には、医療界で働く職業人の職業被曝は含まれないのである。
<10> 放射線取扱主任者は、海外において Radiation Safety Officerなどと呼ばれることからも分かるように、わが国では「放射性同位元素」と「核燃料物質」に
2分されている放射性物質の種別に関係なく、その安全管理に必要な知識と技能を有しているとみなされている
放射線取扱主任者の国家試験には核燃料はカバーされていない。 しかし、核燃料物質に放射性同位元素を加えての放射性物質や放射線の安全管理に関して、一定水準以上の知識と技能の保有を求める「原子炉主任技術者」や「核燃料主任秘術者」の国家試験では、放射線取扱主任者(第1種)の免状保持者に対して試験免除の措置が取られていることはあまり知られていない。
1999年に起きた JCO臨界事故は、発注者が受注先に派遣した放射線安全管理の専門家は、放射線障害防止法の求める要件を満たす国家資格保有者であったが、縦割りにつくられている制度設計と運用に係る不適切さが生んだ悲劇として記憶されるべきである。
また、我が国の制度設計においては、医師の免許保有者は、放射線取扱主任者(1種)の免状取得者と同列に扱われているが、医学教育の実態や国家試験の内容を見る限り、問題なしとは言えないものである。
このことは、例えばIVRといわれる先端的医療技術がこの国で使われ始めた時、MD(医師)の中に過剰の職業被曝を受ける者が多発したことからも明らかである。
2015年04月15日 追記:国は 2年程前にこの点(国試の方策について)は“改善”を施しているようです。
|
| 2015.04.17 改訂 |
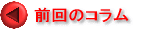 |
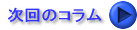 |
|
 |
|
|
|

