|
|
 |
国難“3.11”から3年経過して今考えること
加藤和明
2014年04月21日 |
- 1974年に「原子力船むつ」が“中性子線漏洩”のトラブルを起こした後、政府の調査委員会が出した報告書(問題点が少なくないと考える)に基づき、お役人が作った(三権分立が建前と成っているが実質的に立法したのは行政であった)法律(この法律で原子力安全委員会ができた)も、1999年に起きたJCO臨界事故の後、同じように作られた「原災法」も、“形だけは整えたが魂が込められていないもの”だった(2000年02月だったか、求めに応じ産経新聞紙上で当時の飯田論説委員との対談で意見を述べた)。
- お役人の行動指針(行動の指導原理)は、平時には大過なく、非常時には立派な法律を作ることであり、“立派”の判定基準は“予算とポスト”を沢山取ってくること、である。上記の議論で取り上げられた「原災法」で導入された役所側の重要ポストに在った方も、事業者側に任年を義務付けたポストに在った方も、それ以前から、国の制度設計に盛り込まれていた「原子炉主任技術者」や「核燃料主任技術者」もその存在の影が全く見えなかった。
- 「原災法」で導入された“任務の重い役”には、十分条件はおろか必要条件すら規定されていなかった。
- 「原子炉主任技術者」(A)や「核燃料主任技術者」(B)は、この国で最も難しい国家資格の一つとされているが、“放射性物質の安全管理”にかかる科目の試験では、「放射線取扱主任者」(C)の資格所有者には受験が免除されている。世界の他の国々と同様、この国でも、基準量を超える放射性物質は使用等の規制対象とされるが、この国の制度設計(具現化されたものが法令やそれに基づいて発せられる行政指導)では、元素の別によって「放射性同位元素」と「核燃料物質」に2分している。(C)の国家資格は、「放射性同位元素」についての“安全管理”に必要なことだけを資格の要件としていて、「核燃料物質」の安全管理上最重要な“核分裂連鎖反応”やそれに関わる“臨界”についての学習は受けていない人が大多数である。このような背景を考慮せずにつくられ、運用されてきた“制度”の欠陥が“JCO事故”の根本的な理由であるが、学界も官界もマスコミも取り上げることをしなかった。
- 序に言えば、この国の法令における概念規定は“帰納法的”であって、具体の羅列で行われることが多い。現在、人体に放射線を当てることが法的に認められているのは医師と診療放射線技師だけであるが、後者の国家資格を得るための試験に、暫く前まで“定番問題”の一つとされていたのが「次の中で放射線でないのはどれか?」というのがあり、中性子がこの法令では放射線に指定されていないことを知っているか否かを問うものであった。
- 今週、つくば市にあるKEKでは、保有する核燃料物質について、IAEAの査察を受けることになっているそうだが、事前の打合せ(?)で、「Th-230を核燃料物質のカテゴリーに入れているのがおかしい(他の核種もある)」との指摘があって、まずそのことで叱られなければならない」のだそうだ。実はTh-230をα線源として購入したとき、当時の科技庁担当官から日本では核燃料物質の定義を核種ではなく元素で行っているのだから放射性同位元素としての使用許可願いでは受け付けられないと拒否されたのであった。
- 単位power当たりでいうと、1GW(日本の習慣で言うと100万kW)級の原発と生成中性子の収率がほぼ同じ(原理的に誘導放射能についても当てはまること)である、高エネルギー陽子加速器(電子加速器の場合は働く力の違いにより2桁下がるが)は、国の指定する“特定放射線源”として使用等を規制する担当法は、“原発”や“核燃料物質”を扱う「原子炉等規制法」(D)ではなく“放射性同位元素等”を対象とする「放射線障害防止法」(E)である。“核燃料物質”は“原子炉等”の“等”に、“加速器”(法律用語では「放射線発生装置」は“放射性同位元素等”の“等”に押し込まれているのである。
- 「放射線障害防止法」では、所管の“特定放射線源”の使用許可申請に当たって「使用目的」などに並んで「地崩れのおそれ」と「浸水のおそれ」についても記載を求められる。KEK(1971年設立)では1972年に最初の許可申請(当時は文部大臣名で)行い、以後これまで、約300回変更の許可申請を繰り返してきた。担当官との事前内合わせを経て、「地崩れのおそれ」と「浸水のおそれ」についてはともに「なし」との記載で許可を頂くことが出来た。しかし、東京電力福島第一原発が“3.11”に被災し、過酷事故(1FND)を起こしたとき、政府は「過酷事故に対する安全対策は(許認可を受けた)事業者の裁量に委ねてあるのだから」との理由で、「“事後処理の責任”は事業者(東電)にある」との論理を展開した。この考えが法律(E)の運用にも敷衍されるとするなら、地崩れや浸水が、想定外の事象として実際に起き、周辺の住民を含め広く国民の間に迷惑・損害を与えることになったときには、「なし」と書いたのだから、その後始末はお前さん(許可使用者)がやりなさいと言ってくることが許されることになる。そして、もしそうであるなら、そもそも、申請書にそのような記載を要求する必要はないということになる。また、今日においても、あくまで要件の一つに据える、と言うのであれば、許可の要件を明示すべきである。使用目的に「武器の開発」と書かれたときには、審査の担当官は許可しないだろうと思うが、目的についても許可の要件(判定基準)は明示されていない。防衛省の研究所で行われるものがどのように扱われるかについては、会計検査院の会計検査が誰によってどの様に行われているのか、についてと同様に、国民の多くは関心を持たない。
- さて、19年前の阪神・淡路大震災は実質3年で“復旧・復興”を果たし、91年前のあの関東大震災でも7年後には瓦礫を埋め立てて作った山下公園の落成祝賀を執り行うことが出来た。また69年前の国難(大東亜戦争の敗戦)を思い起こせば、今回の災害“3.11”に対し、国が行ってきた諸々の施策はなんとお粗末なことかと思わざるを得ない。敗戦から3年過ぎた当時の日本は、もっと明るく、誰もが明日は今日よりbetterと信じることができた。将来を見通せないとき、それが不安の素となって人々は希望を失い、国は活力を失う。この3年間の来し方と現在のこの国の在り様をマノアタリにすると、収束には10年以上間違いなくかかる。その長さとそれをもたらす困難の由来・内容を考えるとき、今を生きる日本人にとっては、2011年の“3.11”(1997年の3.11にも原子力の大事故があったが、今それを思い出す人は少ない)は、69年前の国難、740年前の国難(元寇)と並べて然るべき「三大国難」といってよい(と考える)。
- 災害は、天災・人災の別を問わず、あらゆる生物にとって巨大なリスク要因である。ここでいう「生物」は“生命の営みを続けているもの”すべてを意味し、ヒトについていえば、個体としての人だけでなく、人の集まりである組織や社会、さらには都市や国家をも含むものとしている。リスクとは、その“生命の営みを脅かす事象に遭遇する可能性”を意味する。災害に付随するリスクは、事象の種類や性質、測度としてのリスク評価に影響を与える条件の時間的推移に依存し、また、あまたある他のリスクとの間に、多くの複雑なtrade-off関係が存在することから、その合理的な管理手法の構築は容易でない。安全や安全管理の基準と言うものは、社会と当事者の間で結ばれる“契約”でもあり、社会の安全についての意識も時代の流れとともに変化する。
- 天災“3.11”は東電の1Fを破壊し、ドミノ倒しで放射線防護に係る国の制度設計の不適切さを露呈させた。放射線防護のシステムは「原子力は災害(過酷事故)を起こさないという“安全神話”をexplicitlyに前提として」つくられたものであることから、これで「安全神話」は死んだ、死んで呉れた、と思った。多くの識者も死なせなければならないと叫んでいた。1年半過ぎて、原子力規制委員会(NRA)がつくられ、委員長が「世界で一番厳しい規制基準」と自慢する新しい規制基準が作られ、原発の再稼動の適否などを検討している。しかし、いってみれば、これは、災害生起の予想頻度を1000年に1回から2000年に1度に変えたようなもので、「安全神話」の放逐には結びつかない。安全神話は死なせることができないでいる。肝心の「安全哲学の構築」は依然としてできないままであり、早期に放逐されるべき「危険神話」が依然として猛威を振るっている。国難“3.11”の困難克服の最大の障害となっているのは“放射線との付き合い方”に係る困った呪縛であるといってよい。
- 生命を持つもの(広義の生物;組織や国家なども含む)はみな“命を失う可能性”すなわちリスクを抱えながら生きている。リスク・フリーの生活というのは命を失って初めて手に入るものであり、歳をとること、すなわち加齢(aging)そのものが、リスク要因の一つなのである。
人は誰しも何時の日にか死を迎える定めとなっていることを、人々は経験的に知っている。そして、「死を迎えるのは1回限り」という“シバリ”があることも。命を失うことに繋がる物事(リスク要因)は無数といってよいほど沢山あり、一つの要因についてリスク低減の方策を講じると、結果として総合的なリスクの値を高めてしまうことがあることも知られてきた。一つのリスク要因についてのみリスクの最小化を図るというのは、往々にして意味を持たず、有限である財的資源や人的資源の合理性を欠く配分(浪費)となりかねない。
安全論では、絶対的安全の追求を目標とはしない。絶対安全とはリスク要因を完全に放逐することである。交通事故をゼロとするためクルマや飛行機の使用や存在を認めないとするようなことを意味する。
人知の及ばぬ災害(天災)や、数々の束縛条件(利用できる人的資源や財的資源、科学や技術の状況、等)の下で出来る限りの対策を講じるにしても、どこかに割り切りの線引きが必要となる。原子力安全の専門家は、過酷事故に対する安全対策を講じる際に、その線引きの外に置かれたリスクを“残余のリスク”と呼んだ。そのリスクが顕在化したときには、6500万年前にユカタン半島の海岸近くに直径10kmの巨大隕石が落ちて、個の命だけでなく種の命まで奪われてしまった恐竜の思いを抱く(宿命として受け入れる)しかないと私は達観する。
話を戻す。安全対策に割り切りが必要であるなら、対策を考慮する災害の振り分け・線引きが不可欠となる。そして、対策は、線引きの内外の双方に対して、最善・最適になされなければならない。安全対策に“想定外”の逃げ場を用意することは許されないのである。そこで強調したいのは、その線引きを超える事象(災害)が起きたときには、その起因が天災であれ人災であれ、事後の処置に責任を負うべきものは国家であるということである。国家・国民の安全に責任を負うべきは国であると言う論理の帰結である。
国の金庫に金がないとか少ないといったことが議論の根底の置かれるのは困ったことである。概念規定や論理の運びに厳密さを欠き(関係者がそれぞれの思惑を秘めて意図的に曖昧さを残すのである)物事の処理がその場凌ぎの対症療法的なもので済ませることが多い。また、調査捕鯨や死刑制度賛否やSTAP細胞騒ぎの議論を見ても分かるように、この国の議論は論理の対決よりは感情論の対決であることが多い。「牛や豚の肉は食べるのに何故鯨は駄目なのか」とか「皇后陛下の父親である日本人判事が渋い顔をしていた」といったニュースが流されるが、問題とされているのは「“調査”の名目で“商業”をやっている」という建前と本音の乖離である。海外の国々でもこの種の乖離は見られるし、二枚舌外交・Double
Standardに見えることも少なくないが、詭弁と思われることなど厭わずに、factとlogicの整合性確保には苦心しているように見える。国会で「自衛隊が派遣された場所は戦場じゃないのか」と問われた首相が「自衛隊は憲法で戦場に派遣できないことになっている。だから、自衛隊がいる場所は戦場ではない」と答弁したり、法治国家を標榜し「遵法精神が旺盛であることが日本という国の誇り」と豪語する一方で、「人の命は地球より重い」との論理で、(日本の航空機をハイジャックした日本人)テロリストを、それも人質の身代金を要求通り持たせて、釈放し、世界の顰蹙をかったりした結果が、今日のこの国の外交上の困難を招いている主因であると考える。
一方で、歴史が教えることは“勝者の論理が正義となる”ということであり「勝てば官軍」である。世界で覇権を握った者(Super-Power:SP)は“不法”や“無法”をものともしない。20世紀の世界に幅を利かせた二大SPの力量低下は誰の眼にも明らかで、最近は別の国が、WWⅡ戦勝国クラブの1員であること笠に着る如く、次のSPを目指しているかの如く、かつての二大SPを見習い始めている感がある。日本は国際協調をbaseに平和の維持を図ろうとしてきたが、日本で「国際連合(国連)」と呼び慣らしているUnited
Nationsを中国では今も「連合国」と表現していること、その安全保障理事会で“拒否権”という強大な権限を付与されている常任理事国が戦勝国に独占され続けられている、といった現実を忘れてはいけないとも思うのである。
|
| (2014年04月26日 改訂) |
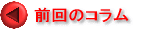 |
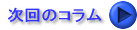 |
|
 |
|
|
|

