|
|
 |
「1ミリシーベルト呪縛問題」について考える
加藤和明
2013年10月06日 |
国は、1F事故の後、一般人に対する“追加被曝線量”の規制値として、年間1ミリシーベルトという値を定めた。これが、3.11災害の復興に大きな妨げとなっていることに、政・官・学を含め、多くの人が気付きながら、様々の“壁”に阻まれて身動きができない状況に立ち至っている。
放射線防護に係るこの国の制度設計は、原発では過酷事故を起こさないことを前提にするなど、平時を前提に作られ運用されてきたものである。3.11に1Fが被災し過酷事故を引き起こしたことにより、適用に限界が有ることが明らかとなり、その意味では、性能・有効性を著しく毀損したと見ることもできる。
初めにあげた困難の招致は、有効性を欠いて適用不可となっている対象に、制度設計の再構築を検討することもないまま、いきあたりばったりに、つぎはぎの手当(「1F事故起因放射性物質」「追加線量」などの新概念導入や「職業的被曝」の再利用、など)で対症療法的措置を講じていることが、根本の原因である。
以下は、現行の(放射線防護に係る国の)制度設計見直しの提案である。これにより、表記課題の解決も図られるものと考える。
- 『追加線量』の概念導入と使用を取り止める⇒これに伴い「追加線量として受ける被曝線量は少なければ少ないほど良い」を指導原理として、3.11後に国が定めた、各種管理基準は消滅させる
- 『職業人』『一般人』などの(放射線安全管理の便と称して導入されている)“人の区分”を廃止する
- 個人についての放射線被曝管理の目標を、「放射線影響学」の専門家や関係機関がいうところの「確定的影響」の発現阻止に限定する
- 同じく「放射線影響学」の専門家や関係機関がいうところの「確率的影響」(stochastic effects:定着して邦訳はよくない)に付随するリスクの管理は環境保全の体系に組み入れる
- (様々のリスク要因を抱える)環境の保全基準は、リスクの総合的評価に基づき、地域社会の意思により、地域ごとに決定できるものとする
<補足説明>
- 現行(as of “3.11”)の「放射線防護に係る制度設計」は、“放射線そのもの”ではなく、“特定の放射線源”の使用等を規制することを基本とするもので、自然・戦争・事故起因の放射線被曝は対象外としている。
医療起因の放射線被曝は対象に取り込んではいるが“特別扱い”となっている。
- (狭義の)原子力を仮に止めたとしても付き合いを止めることのできない放射線への防護策(=制度設計)を“原子力の傘”の下に置くことの是非も検討課題
/ 生活空間がISS(自然放射線のレベルが地表のそれより2桁上)や “1FのND(原子力災害=過酷事故)”という想定外の事象生起により、複数の県にまたがる領域で、環境放射線レベルが様々の割合で上昇した、という現実を直視する必要がある。
- ここでは、リスクを「生物に生命維持を困難にする事態が生じる可能性」と定義する。 生物とは広く“生命を持つもの”を意味し、人間の場合には、個人だけではなく、人の集団である社会をも含むものとして、概念を規定し、家庭や地域社会から、会社などの営為目的で集まっている集団・組織、さらには国家・民族などといった、までを含むものとしている。
- 「便益の追求と危険の回避」は、すべての生命体が保有する基本的欲求である。 生物の場合は「本能的欲求」となっており、人の場合は「基本的人権」と見做され、日本では憲法が保証しているものである。
- 被曝線量の測定・評価は、環境に存する放射線の寄与を排除して行う、というのが従来からの慣わしである。 3.11後の今日でも“暗黙の了解”であると言わんばかりに受け取られ、関係者は盲目的にこれに従っている。
NDを引き起こしたことにより“環境放射線”のレベルが極端に上昇してしまった 1F施設内での“職業被曝線量”の測定・評価の実態、宇宙飛行士に対する“職業的被曝線量”の測定・評価の実態、福島県や近隣県の住民が受ける追加線量の測定・評価に取られている方法の実態等や、追加線量を導入した国の施策の意義と有効性に対するあちこちからの疑問の提起、などが、放射線管理学にとっての喫緊の課題となっている。
- 世間(政・官・学・産・マスメディア)では、放射線影響学と放射線管理学を区別せず、これらに関わる専門家を「放射線防護」の専門家として一括りにしているが、両者は全く別のものと言って良いものである。
前者は科学であり、後者は工学であり実学である。
- 提案では、確定的影響に係る防護の目標を、現行の「発現の絶対的阻止」から“絶対的”を排除している。 一見“規制の緩和”と見える。 実際そうなっているのであるが、一般社会で日常行われている“安全管理”の実態とは、これで十分調和が取れていると考える。
例えば火の使用において“火傷”の阻止は絶対阻止とはしていない。 そうでなければ家で天麩羅を揚げることなどできなくなる。 うっかりしてヤケドをしたとしても適切な処置をすれば通常は数日で回復するし、ときには、もっと大事なこと(当事者にとってより価値の高い行為)をするために敢えて火傷を負うリスクを取ることもあるのである。
|
| 2013年10月10日 |
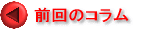 |
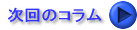 |
|
 |
|
|
|

